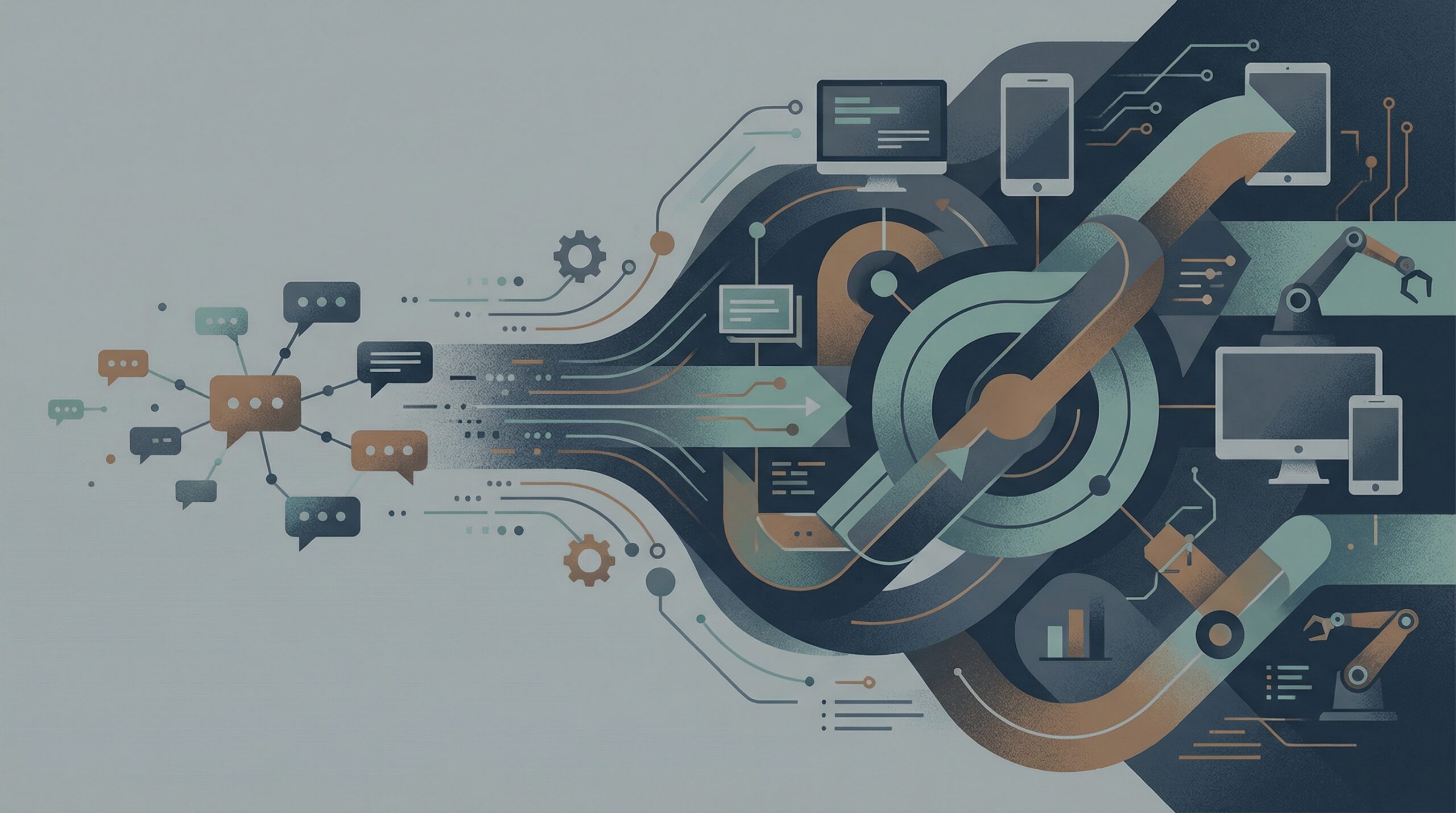生成AIの活用は、単なる「対話(チャット)」から、アプリやデバイスを操作してタスクを完遂する「行動(アクション)」のフェーズへと移行しつつあります。LenovoやMotorolaなどが示す最新の動向を端緒に、AIエージェントがもたらす業務プロセスの変革と、日本企業が直面するガバナンス上の課題について解説します。
対話型AIの限界と「Agentic AI」の台頭
ChatGPTの登場以降、多くの日本企業が生成AIを導入しましたが、その用途の多くは「文書作成」「要約」「アイデア出し」といったテキスト処理に留まっています。しかし、現在グローバルで注目されているのは、AIが単に言葉を返すだけでなく、ユーザーに代わって具体的な操作を行う「Agentic AI(自律型AIエージェント)」への進化です。
LenovoやMotorolaなどが開発を進める次世代のアシスタント機能は、このトレンドを象徴しています。これらは、従来のチャットボットのようにテキストボックスの中で完結するのではなく、デバイス内のアプリケーションを横断し、ファイル転送やアプリの操作といった「実タスク」を遂行することを主眼としています。これは、大規模言語モデル(LLM)に加え、インターフェースを操作するためのモデル(Large Action Modelなど)を組み合わせたアプローチと言えます。
デバイスメーカーが握る「ラストワンマイル」の覇権
なぜソフトウェア企業だけでなく、ハードウェアメーカーがこの領域に注力するのでしょうか。それは、AIが「行動」するためには、OSやアプリケーションへの深いアクセス権限が必要だからです。
クラウド上のAIサービスだけでは、ローカルPC内の特定ファイルの操作や、認証が必要な社内システム間の連携にセキュリティやAPIの壁が存在します。しかし、デバイスそのもの(PCやスマートフォン)に統合されたAIであれば、ユーザーの操作を模倣し、異なるアプリ間でのデータの受け渡しをスムーズに行える可能性があります。これは、API連携が未整備なレガシーシステム(SaaS化されていない基幹システムなど)を多く抱える日本企業にとって、RPA(Robotic Process Automation)の進化系として機能する可能性を秘めています。
日本企業における活用とリスク:ガバナンスの再考
日本企業がこのような「行動するAI」を導入する場合、最大の懸念点はセキュリティとガバナンスです。従来の「テキストを生成するだけ」のAIであれば、誤情報(ハルシネーション)が含まれていても人間が確認して修正すれば済みました。
しかし、AIが「メールを送信する」「決済を承認する」「ファイルを移動する」といったアクション権限を持つ場合、一度の誤動作が取り返しのつかない実害をもたらすリスクがあります。特に日本の商習慣では、確実性と責任の所在が厳しく問われます。したがって、AIにどこまでの操作権限を与えるか、どのプロセスで「Human-in-the-loop(人間の承認)」を必須とするかという、より厳密な業務設計とガバナンスルールが必要になります。
日本企業のAI活用への示唆
AIのトレンドが「チャット」から「アクション」へ移行する中で、日本企業の意思決定者や実務担当者は以下の点に留意すべきです。
- 「つなぐ」コストの削減:API連携が困難な古いシステムや、分断されたSaaSツール間の連携において、デバイス横断型のAIエージェントが「知的なRPA」として機能し、業務の分断を解消する可能性があります。
- ハードウェア選定の視点変化:PCやスマホの選定基準が、単なるスペックから「AIエージェントがOSレベルで統合され、業務効率化に寄与するか」という点にシフトする可能性があります。
- 「実行」のリスク管理:AIによる自動操作を前提とした場合、従来の「情報漏洩対策」に加え、「誤操作・誤発注防止」のための権限管理やログ監視の仕組みを早期に検討する必要があります。