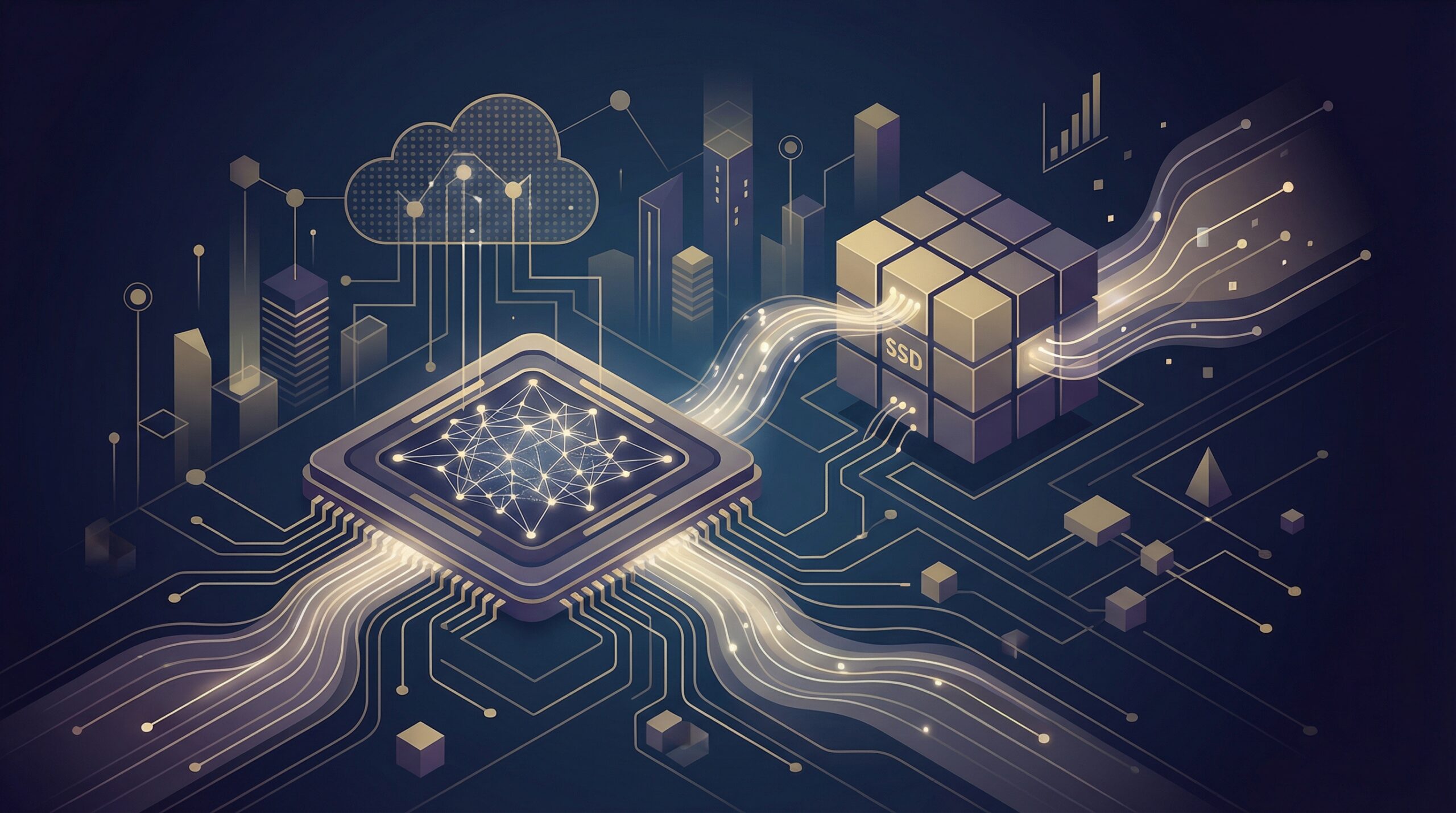ストレージコントローラー大手のPhisonが、SSDをGPUメモリの拡張領域として活用する技術「aiDAPTIV+」をPC環境へ拡大しました。高騰するGPUリソースへの依存を減らし、汎用的なハードウェアで大規模言語モデル(LLM)を動作させるこのアプローチは、コスト制約やセキュリティ要件の厳しい日本企業にとって、AI導入のハードルを下げる現実的な選択肢となり得ます。
メモリ不足という「生成AIの壁」に対するストレージ側からの回答
生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の活用において、企業が直面する最大の物理的なボトルネックは「GPUメモリ(VRAM)の容量不足」です。高性能なモデルを動かすには高価なHBM(広帯域メモリ)を搭載したGPUが必要となりますが、昨今のGPU不足と価格高騰は、多くの企業にとって導入の障壁となっています。
こうした中、NANDフラッシュコントローラー市場をリードするPhisonは、独自技術「aiDAPTIV+」の適用範囲をサーバーからPC(ワークステーション)領域へと拡大しました。この技術は、LLMの推論やファインチューニング(微調整)において、不足するGPUメモリをシステムメインメモリ(DRAM)や高速SSDで補完するものです。具体的には、モデルのレイヤーを分割し、計算に必要な部分だけをGPUに送り、残りをSSDに退避させることで、限られたVRAM容量でも巨大なモデルを処理可能にします。
記事にあるように、ストレージベンダーのStorONEなどがすでにエンタープライズ製品に採用していますが、これがPCレベルにまで下りてきたことの意味は小さくありません。
「クラウド一辺倒」からの脱却とエッジAIの現実解
日本国内の多くの現場では、セキュリティポリシーや通信環境の制約から、クラウドにデータを上げられないという課題があります。しかし、オンプレミスで十分なGPUサーバーを構築するには数千万円単位の投資が必要です。
Phisonのこの動きは、一般的なワークステーションやハイエンドPCに搭載されたSSDを活用し、ローカル環境で700億パラメータ級(70B)のLLMを運用可能にすることを目指しています。これは、製造業の工場内(OT領域)での異常検知システムや、金融・医療機関など機密性の高いデータを扱う部門内での「専用LLM」構築において、ハードウェアコストを劇的に下げる可能性を秘めています。
速度とコストのトレードオフをどう評価するか
ただし、実務的な観点からは「魔法の杖ではない」ことも理解しておく必要があります。SSDの転送速度は、PCIe Gen5などの最新規格であっても、GPU内部のHBMやシステムDRAMと比較すれば低速です。そのため、SSDへオフロード(データ退避)するアプローチは、超低遅延が求められるリアルタイム処理には不向きな場合があります。
一方で、社内ドキュメントの検索・要約(RAG)や、夜間のバッチ処理によるデータ分析、あるいは開発段階でのPoC(概念実証)においては、多少のレイテンシ(遅延)増加は許容範囲内であることが多々あります。「最高速度」よりも「扱えるモデルサイズとコスト効率」を優先する場合、このアーキテクチャは非常に合理的な選択肢となります。
日本企業のAI活用への示唆
今回の技術動向は、日本のAI活用推進者に対して、ハードウェア選定における新たな視点を提供しています。
1. 「円安・GPU高騰」時代のコスト最適化戦略
すべてを最高スペックのGPUで解決しようとせず、用途(推論か学習か、リアルタイムかバッチか)に応じて、SSDを活用したハイブリッドなメモリ構成を検討することで、インフラコストを大幅に圧縮できる可能性があります。
2. 「ローカルLLM」によるガバナンス強化
PCやエッジサーバーレベルで高度なLLMが動作すれば、個人情報や技術情報を外部に出すことなくAI処理を完結できます。これは、日本の厳しい個人情報保護法や企業の内部統制ルールに準拠しながらAI活用を進めるための強力な武器になります。
3. PoCの「死の谷」を越えるための環境整備
高額なインフラ投資の決裁が下りず、PoCが進まないという悩みは多くの日本企業に共通しています。既存のワークステーションに安価なSSDを追加するだけで検証環境が構築できれば、スモールスタートで実績を作り、本格導入につなげるアジャイルな開発スタイルが促進されるでしょう。