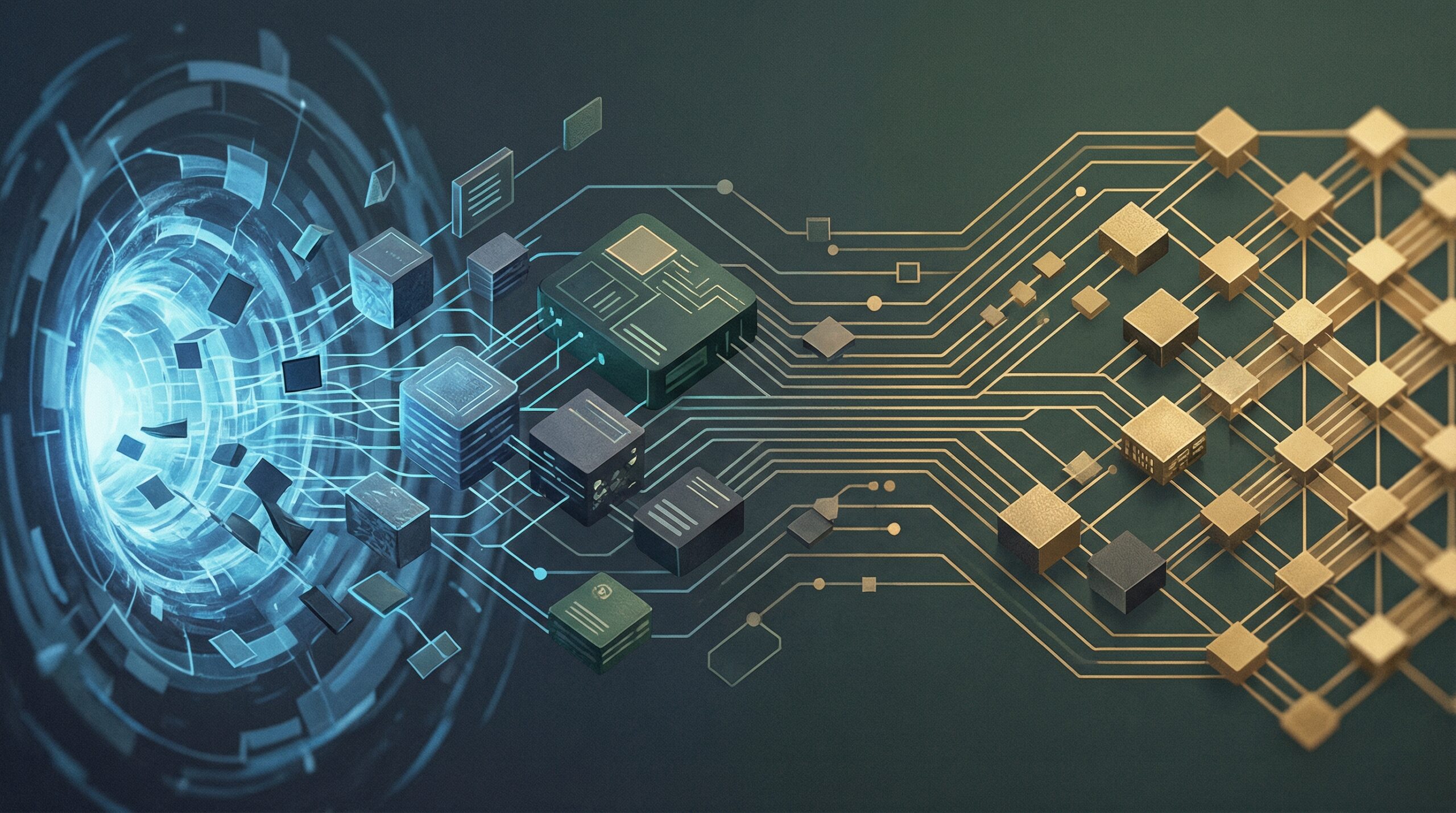生成AIの活用フェーズは、単なるチャットボットから、自律的にタスクを遂行する「エージェント型」へと移行しつつあります。しかし、実運用においてはLLM特有の「不確実性」が壁となります。本記事では、GraphBitなどの最新ツールが採用する「決定論的(Deterministic)アプローチ」と「グラフベースの検証」に焦点を当て、日本企業が信頼性の高いAIシステムを構築するための要諦を解説します。
AIエージェントの実装における「確率」と「確実性」のジレンマ
現在、世界のAI開発トレンドは、ユーザーの指示を待つだけの受動的なAIから、目標に向かって自律的に計画・実行を行う「エージェント型ワークフロー(Agentic Workflows)」へと急速にシフトしています。しかし、企業がこれを本番環境(Production)に導入しようとする際、最大の障壁となるのがLLM(大規模言語モデル)の「確率的な挙動」です。
LLMは本質的に、次に続く言葉を確率で予測する仕組みであるため、同じ入力をしても出力が揺らぐことがあります。クリエイティブな作業にはこの「ゆらぎ」が有用ですが、定型業務や基幹システムへのデータ入力といったミスが許されないタスクにおいては、致命的なリスクとなります。
そこで注目されているのが、今回のテーマである「決定論的ツール(Deterministic Tools)」と「グラフ構造」を用いたアプローチです。これは、すべてをLLMに任せるのではなく、確実な処理が必要な部分は従来のプログラムコード(決定論的な処理)で固め、LLMはあくまで判断や柔軟な解釈が必要な部分(オーケストレーション)に限定して利用するという設計思想です。
検証可能な「実行グラフ」による品質担保
「GraphBit」などの最新のフレームワークが提唱する方法論では、AIの処理フローを明確な「グラフ(ノードとエッジでつながれた図)」として定義します。これにより、処理の流れが可視化され、どこでどのようなデータ処理が行われたかが追跡可能になります。
特筆すべきは、LLMを「オプション(任意の要素)」として扱っている点です。たとえば、データの検索や計算といったタスクは、ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクがあるLLMではなく、信頼できる外部ツールやスクリプトに任せます。そして、その結果を人間が理解しやすい形にまとめる最終工程のみにLLMを使用するといった使い分けが可能になります。
また、こうしたツールでは「オフラインモード」での動作確認が重視されています。LLM APIに接続せずとも、ロジック部分(決定論的な部分)だけでワークフローが正しく機能するかをローカル環境で徹底的にテストできることは、開発コストの削減だけでなく、セキュリティの観点からも極めて重要です。
日本企業における「ブラックボックス化」の回避
日本の企業文化、特に金融や製造、インフラといった信頼性が重視される業界では、AIの「説明可能性(Explainability)」が強く求められます。「なぜAIがその判断をしたのか」がブラックボックスのままでは、稟議を通すことも、事故時の責任説明も困難だからです。
すべてをLLMのプロンプトだけで制御しようとする「プロンプトエンジニアリング依存」のアプローチは、挙動が不安定になりがちで、日本の品質基準を満たすのが難しい場合があります。対して、今回紹介したような処理フローを明示的にグラフ化し、決定論的なツールを組み合わせる手法は、従来のシステム開発における単体テストや結合テストの考え方を適用しやすく、日本企業の開発体制と親和性が高いと言えます。
日本企業のAI活用への示唆
グローバルの技術トレンドを踏まえ、日本企業が実務でAIエージェントを活用する際は、以下の視点を持つことが重要です。
1. 「適材適所」のアーキテクチャ設計
「なんでも生成AIで解決しようとしない」ことが肝要です。数値計算、DB検索、定型フォーマットへの変換など、ルールベースで処理できる部分は既存のプログラム(決定論的ツール)に任せ、LLMは「非構造化データの解釈」や「自然言語への変換」など、得意分野に特化させるハイブリッドな構成を目指すべきです。
2. オフライン検証とコスト管理
開発段階から常にLLM APIを叩いていると、API利用料が嵩むだけでなく、ロジックのバグとLLMの回答精度の問題の切り分けが難しくなります。オフラインで動作するロジック部分を確立してから、最後にLLMを接続する開発フローを採用することで、コスト削減と品質向上を両立できます。
3. ガバナンスと可視化
処理フローが可視化されていることは、ガバナンスの観点からも必須です。どの工程で外部APIを呼び出し、どの工程で個人情報を扱っているかをグラフ上で明示できるツールを選定することは、コンプライアンス遵守の証跡としても機能します。
結論として、AI活用の成功は、AIの「魔法」を信じることではなく、AIを従来の堅牢なシステム開発の中に「部品」として適切に組み込むエンジニアリング力にかかっています。