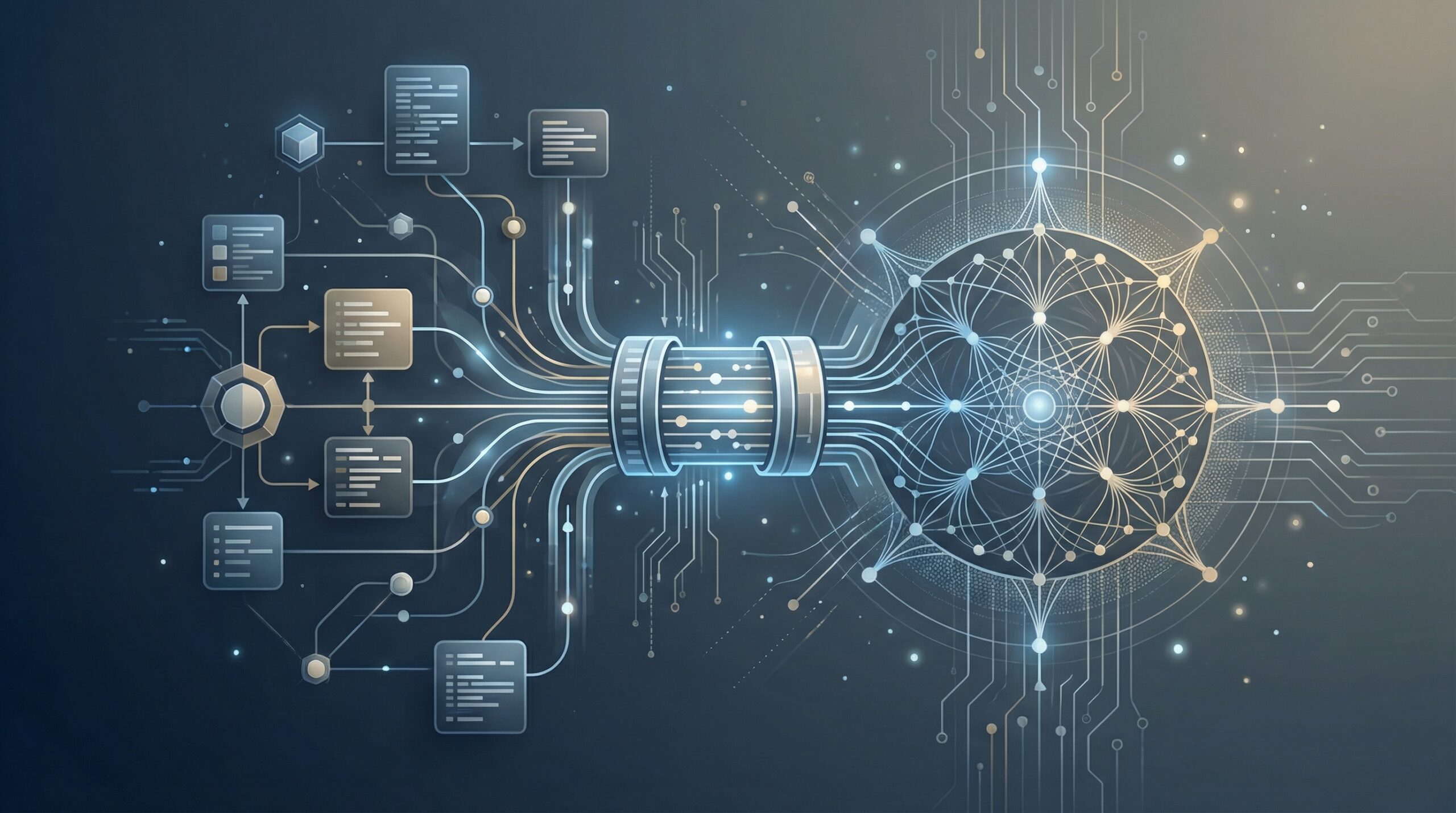Anthropic社が提唱する「Model Context Protocol (MCP)」が、AIと社内システムの連携における新たな標準となりつつあります。本記事では、海外の契約管理システム(CLM)連携の最新事例を起点に、MCPが解決する課題、日本企業がシステム連携を進める際のメリット、そして不可欠なガバナンス対応について解説します。
「個別のつなぎ込み」から「標準化」へ:MCPの登場背景
生成AI活用において、企業が直面する最大の課題の一つが「社内データとの連携」です。これまでは、社内のデータベースやSaaSツール(Google Drive、Slack、GitHubなど)をLLM(大規模言語モデル)に接続するために、ツールごとに独自のAPI連携やプラグイン開発を行う必要がありました。これは開発コストがかさむだけでなく、メンテナンスの負荷も高いものでした。
この状況を打破するためにAnthropic社が2024年後半に公開したオープン標準が**Model Context Protocol (MCP)**です。簡単に言えば、AIとデータソースをつなぐための「USB-C端子」のような共通規格です。この規格に対応していれば、ChatGPTやClaudeといったLLM側のクライアントと、社内の業務システムを容易に、かつセキュアに接続することが可能になります。
事例:契約管理システム(CLM)と生成AIの融合
今回の元記事となるトピックでは、契約管理プラットフォーム(CLM)である「Concord」と、Legal IT Insiderによるウェビナーにおいて、MCPを活用してCLMデータをChatGPTやClaudeに連携する方法が議論されています。
これは法務部門や管理部門にとって非常に示唆に富む事例です。具体的には、MCPを介してCLMとLLMを接続することで、以下のような業務フローが実現します。
- 自然言語での検索:「来月末に更新期限を迎える秘密保持契約(NDA)をリストアップして」とAIに指示するだけで、AIがCLM内のデータを参照し、回答を生成する。
- ドラフト作成の効率化:「A社の過去の取引条件に基づき、業務委託契約書のドラフトを作成して」といった指示に対し、過去の契約データを正確にコンテキストとして取り込む。
これまでは、担当者がCLMからデータをCSVでエクスポートし、個人情報をマスキングした上でAIに入力するといった手間が発生していました。MCPによる直接連携は、こうした「スイッチングコスト」を大幅に削減します。
日本企業における導入の壁と「データガバナンス」
日本企業、特に製造業や金融機関など機密性の高い情報を扱う組織にとって、この技術は諸刃の剣となり得ます。「便利だから」という理由だけで無条件に接続することは推奨されません。
MCPのようなプロトコルを採用する場合、以下の「日本的な」課題への対処が求められます。
第一に、アクセス権限の継承です。部長だけが見られる契約書を、一般社員がAI経由で閲覧できてしまっては重大なコンプライアンス違反となります。MCPの実装においては、元のシステム(この場合はCLM)が持つ権限設定をAI側がいかに遵守するか、あるいは中間層でいかにフィルタリングするかが技術的な肝となります。
第二に、データの二次利用リスクです。商習慣として「外部サービスへのデータ送信」に慎重な日本企業では、連携先のLLM(ChatGPT EnterpriseやClaudeのAPI利用など)がデータを学習に利用しない設定になっているか、契約レベルでの確認が必須です。
日本企業のAI活用への示唆
MCPの登場とCLM連携の事例は、今後の日本企業のシステム開発やAI活用に以下の示唆を与えています。
- 「標準規格」への準拠をシステム選定基準に:今後SaaSや社内システムを選定・開発する際、MCPのようなオープン標準に対応しているか(あるいは対応予定があるか)が、将来的なAI連携の容易さを左右する重要なKPIになります。
- RAG(検索拡張生成)の低コスト化:独自の検索システムを構築せずとも、MCPサーバーを立てるだけで社内ナレッジをAIに接続できる可能性が広がりました。まずは社内規定集やマニュアルなど、リスクの低い公開情報からパイロット運用を始めるのが得策です。
- 「AIガバナンス」の実装:AI利活用規定において「何を入力してよいか」だけでなく、「どのシステムをAIに接続してよいか」という接続許可プロセスを設ける必要があります。情シス部門は、各部署が勝手にMCPサーバーを立ち上げて外部AIと接続しないよう、ネットワークレベルでの監視とポリシー策定を急ぐべきです。
MCPは、サイロ化(分断)された日本の社内システムをAIの力で横断的に活用するための強力な武器となり得ます。しかし、その前提には堅牢なセキュリティ設計が必要であることを忘れてはなりません。