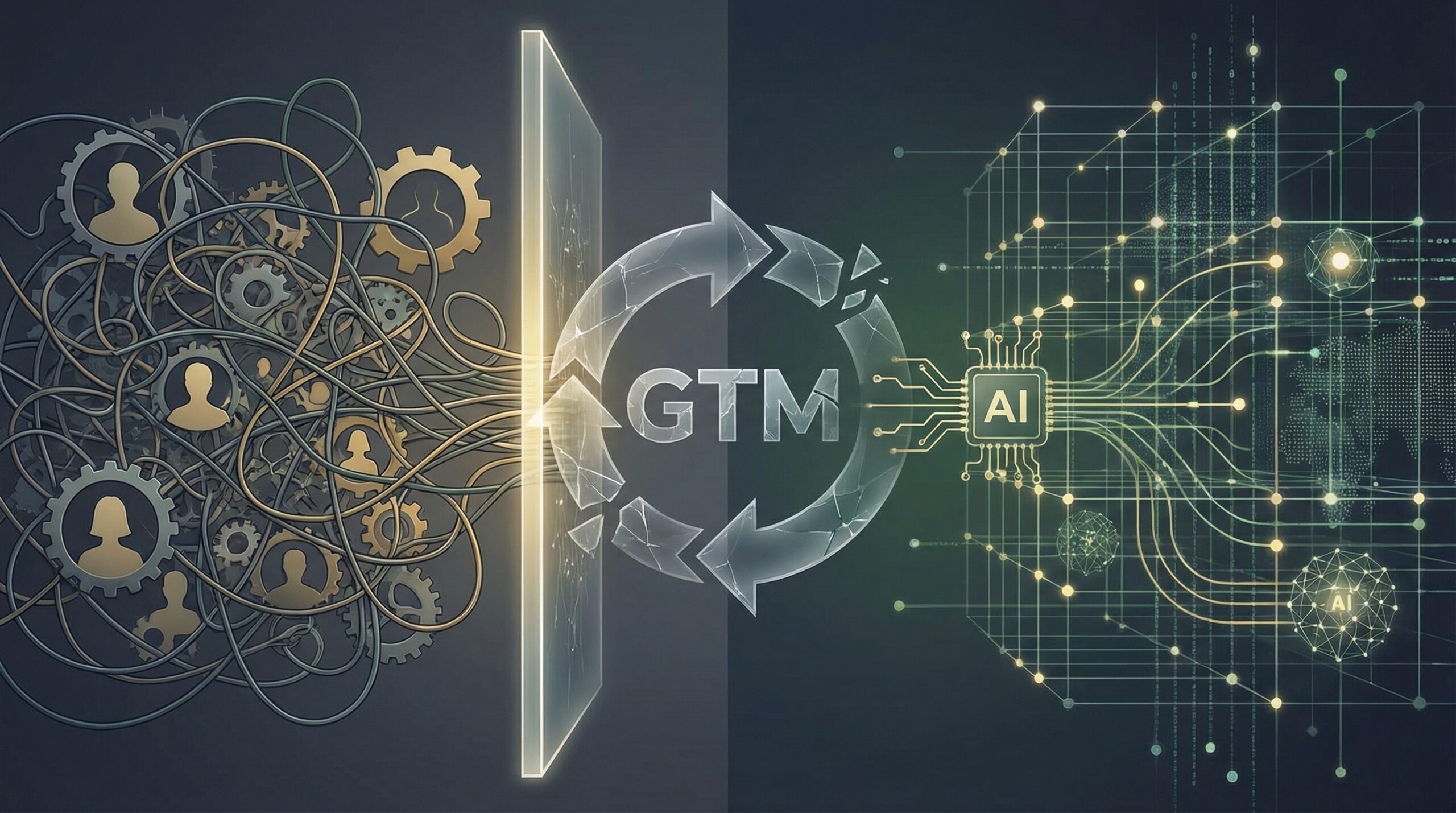GTM(Go-To-Market)領域でのAIエージェント活用が注目されていますが、多くの企業が陥る致命的なミスがあります。それは「人間でも成功パターンが見えていない業務をAIに丸投げしてしまう」ことです。本稿では、AI導入前に問うべき「10人の新人」という思考フレームワークと、日本企業が直面する「暗黙知」の課題について解説します。
AIは「魔法の杖」ではなく「拡張装置」である
生成AIの進化により、営業やマーケティング、カスタマーサクセスといったGTM(Go-To-Market)領域においても、「AIエージェント」の導入検討が進んでいます。しかし、SaaS業界の知見が集まるSaaStrの指摘によれば、AIエージェントの導入において最も頻繁に見られるエラーは、「チームがまだ解決策を見出していない問題を、AIが解決してくれると思い込むこと」にあります。
多くの経営者やマネージャーは、AIを「優秀なベテラン社員」のように捉えがちです。「なんとなくうまくいっていない営業プロセス」をAIに任せれば、魔法のように解決策を見つけ出し、成果を上げてくれると期待してしまうのです。しかし、現状のLLM(大規模言語モデル)ベースのエージェントの本質は、確立されたプロセスの「自動化」と「スケーリング(規模拡大)」にあります。つまり、人間がやっても成果が出ない、あるいはやり方が定まっていない業務をAIに行わせても、失敗を高速かつ大量に繰り返すだけになってしまいます。
「10人の新人」思考フレームワーク
AIエージェントをデプロイ(実戦投入)する前に、必ず自問すべきシンプルな問いがあります。それは、「もし今、10人の経験の浅いジュニア層の担当者(新人やインターン)を雇ったとして、彼らを即座に活躍させられるだけの『プレイブック』が手元にあるか?」というものです。
もし、明確なトークスクリプト、メールテンプレート、反論処理のマニュアル、そして成功への道筋が言語化されておらず、「背中を見て学べ」や「空気を読んで対応しろ」という状態であれば、その組織はAIエージェントを受け入れる準備ができていません。10人の新人が混乱する状況下では、AIエージェントも同様に(あるいはそれ以上に)混乱し、見当違いな顧客対応やハルシネーション(もっともらしい嘘)を引き起こすリスクが高まります。
日本企業における「暗黙知」の壁
この「プロセスの言語化・標準化」という課題は、欧米企業以上に日本企業にとって高いハードルとなります。日本のビジネス現場では、長らく「阿吽の呼吸」や「現場の勘所」といったハイコンテクストなコミュニケーションが重視されてきました。営業活動においても、トップセールスの属人的なスキルに依存しており、そのノウハウが組織知として形式知化(ドキュメント化)されていないケースが散見されます。
AIは「空気」を読みません。AIは与えられたデータとプロンプト(指示命令)に従って確率的に言葉を紡ぐだけです。したがって、日本企業がAIエージェントをGTM領域で活用するためには、まず社内に眠る「暗黙知」を徹底的に「形式知」へと変換する作業が不可欠です。これを飛ばしてツールだけを導入しても、期待したROI(投資対効果)が得られないばかりか、ブランド毀損のリスクすら招きかねません。
日本企業のAI活用への示唆
以上の視点を踏まえ、日本企業の意思決定者や実務担当者は以下の3点を意識してAI活用を進めるべきです。
1. 「AI導入」の前に「業務の標準化」を完了させる
AIに何をさせるか考える前に、人間がその業務をどのように行えば成功するのか、フローチャートやマニュアルに落とし込めるレベルまで解像度を高めてください。AIは「優秀な新人」ですが、教育係(マニュアル)がいなければ機能しません。
2. ハイブリッドな体制作りから始める
いきなり顧客対面の全プロセスをAIに任せるのではなく、まずは「インサイドセールスのアポイント調整」や「一次対応」など、比較的パターン化しやすい部分から適用します。その際、必ず人間が最終チェックを行う「Human-in-the-Loop」の体制を維持し、AIの挙動を監視・修正しながら、徐々に自社専用のプレイブックを精緻化していくアプローチが現実的です。
3. 失敗の責任所在を明確にするガバナンス
AIエージェントが誤った情報を顧客に伝えた場合、それは「AIのミス」ではなく「監督者(企業)の責任」となります。特に日本の商習慣では、誤情報に対する許容度が低い傾向にあります。AIの出力をどの程度信頼し、どこまで自動化するかというリスク許容度を、技術部門だけでなく法務・コンプライアンス部門と事前に合意形成しておくことが重要です。