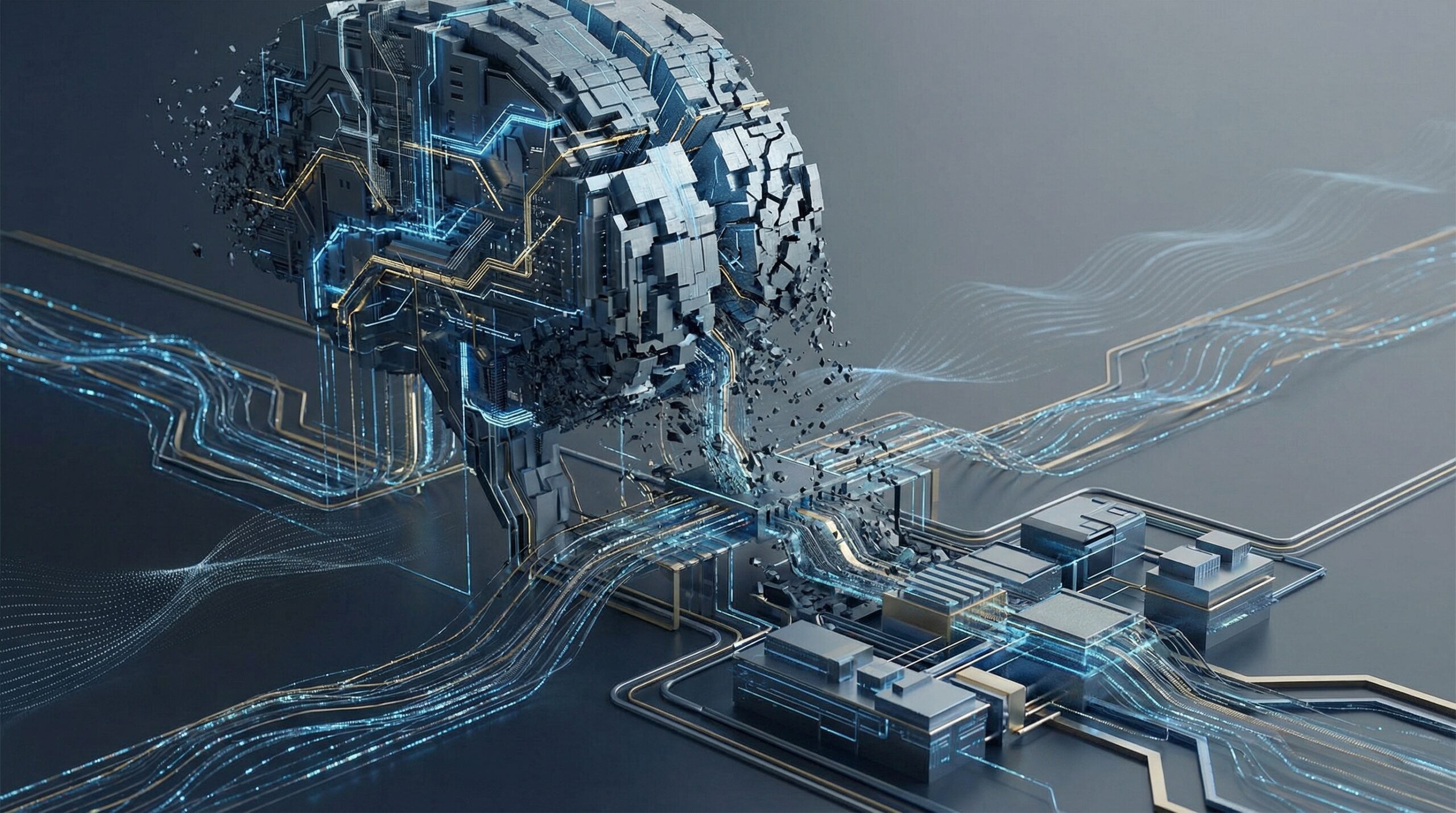生成AIブームが続く中、元SAPのCTOでありVianai Systemsの創業者であるVishal Sikka氏が「現在のLLM(大規模言語モデル)のアーキテクチャは持続不可能である」と警鐘を鳴らしました。単にモデルを巨大化させる競争の限界と、企業が実務でAIを活用する際に直面する「信頼性」や「コスト」の壁について、日本のビジネス環境に照らし合わせて解説します。
「スケーリング則」の限界とエネルギー問題
Vishal Sikka氏がIndia AI summitで指摘した「持続不可能性」の背景には、現在のAI開発の主流であるTransformerベースの巨大モデルが抱える構造的な課題があります。これまでAIの性能向上は、データ量と計算資源を増やせば賢くなるという「スケーリング則」に依存してきました。しかし、その代償として膨大な電力消費と計算コスト、そして学習データの枯渇という問題が顕在化しています。
日本企業においても、円安によるクラウドコストの増加や、国内データセンターの電力供給制約は無視できない経営課題です。単に「最大かつ最新のモデル」をAPI経由で利用するだけでは、ランニングコストが肥大化し、ROI(投資対効果)が見合わなくなるリスクが高まっています。
確率的な「正しさ」と企業が求める「正確性」のギャップ
Sikka氏が以前から提唱しているもう一つの重要な視点は、LLMの本質的な欠陥、すなわち「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」の問題です。現在のLLMは「次に来る単語を確率的に予測する」仕組みであり、論理的な思考や事実確認を行っているわけではありません。クリエイティブな用途では有用ですが、日本の金融、製造、医療といったミッションクリティカルな領域では、99%の精度でも不十分な場合があります。
日本の商習慣では、説明責任やコンプライアンスが厳しく問われます。「なぜAIがその回答を導き出したのか」をブラックボックスのままにしておくことは、ガバナンス上の大きなリスクとなります。Sikka氏の懸念は、確率的なLLMだけに頼る現在のアプローチでは、企業の基幹業務への適用には限界があるという実務的な指摘と捉えるべきです。
ニューロ・シンボリックAIと小規模モデルへの転換
では、次の一手は何でしょうか。業界では現在、巨大な汎用モデル一辺倒から、より効率的で制御可能なアプローチへのシフトが始まっています。一つは、従来のルールベースや論理推論(シンボリックAI)と、ディープラーニング(ニューラルネットワーク)を組み合わせた「ニューロ・シンボリックAI」のようなハイブリッドな手法です。これにより、言語能力はLLMに任せつつ、事実確認や計算処理は確実なロジックで行うことが可能になります。
また、特定の業界データや社内データのみで学習させた「SLM(小規模言語モデル)」への注目も高まっています。パラメータ数を抑えることで、自社サーバー(オンプレミス)やエッジデバイスでの運用が可能になり、セキュリティとコストの両面で「持続可能な」運用が見込めます。
日本企業のAI活用への示唆
今回の提言を踏まえ、日本の経営層やエンジニアは以下の視点を持ってAI戦略を見直すべきです。
- 「なんでもLLM」からの脱却: すべてのタスクを巨大な汎用モデル(GPT-4など)に投げず、タスクの難易度に応じて軽量なモデルや従来のRPA、ルールベース処理を使い分けるアーキテクチャを設計する。
- ハイブリッドな信頼性の確保: RAG(検索拡張生成)などの技術に加え、AIの出力結果を決定論的なプログラムで検証するフローを組み込み、日本企業に求められる品質基準(Quality Assurance)を満たす仕組みを作る。
- コスト対効果のシビアな計算: PoC(概念実証)の段階から、本番運用時のトークン課金やGPUコストを試算し、ビジネスモデルとして成立するかを厳しく評価する。場合によっては、オープンソースの小型モデルを自社でファインチューニングする方が長期的に安価で安全な場合がある。
AIは「魔法」から「実務ツール」へとフェーズが移行しています。Sikka氏の言葉は、技術的な限界を直視し、地に足の着いた実装を進めることの重要性を私たちに教えてくれています。