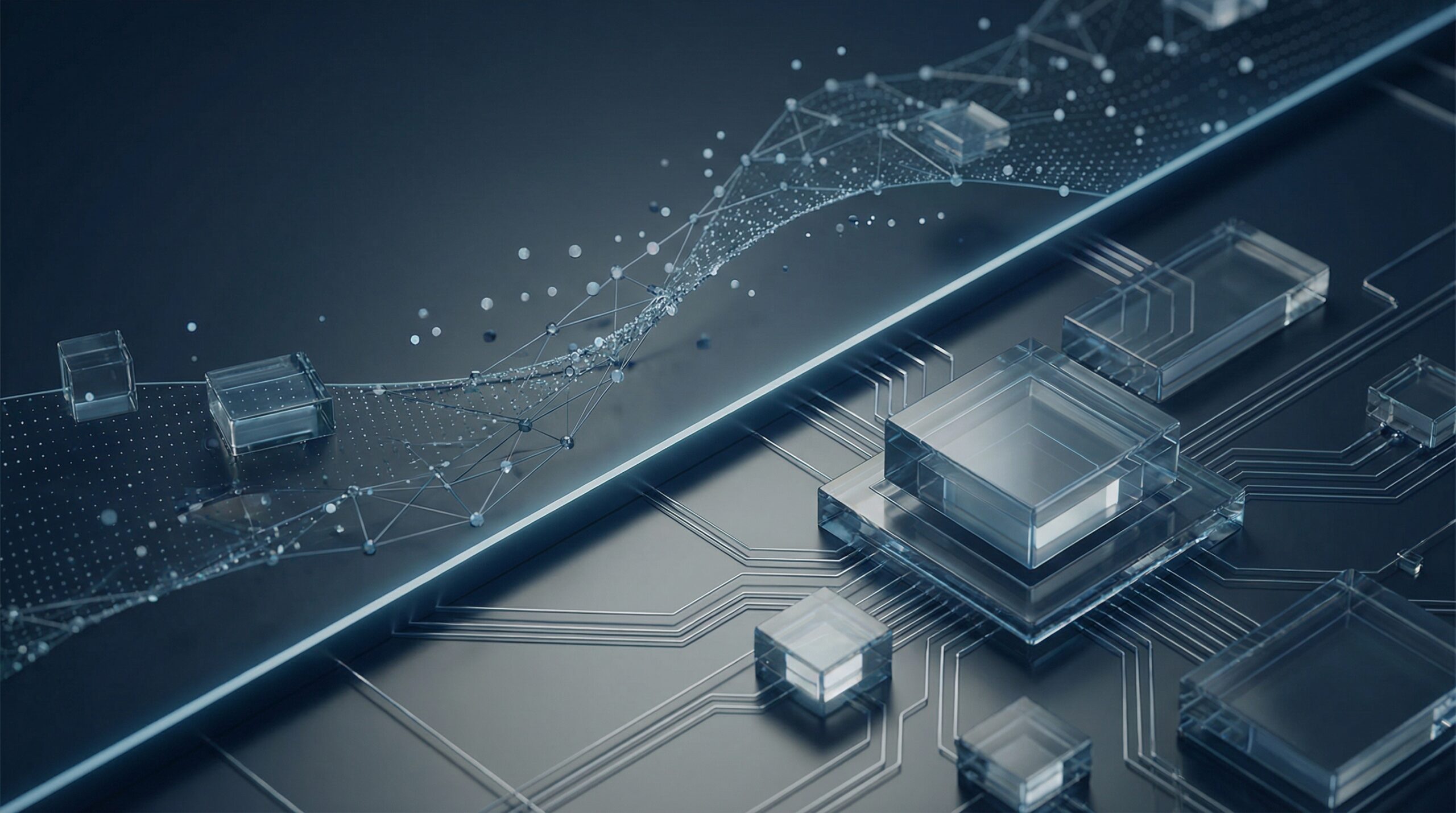米国の連邦地方裁判所が、生成AIに入力したプロンプトや作成されたドラフトは「弁護士・依頼者間秘匿特権」によって保護されないという判断を下しました。これは、法務や知財業務におけるAI利用の前提を覆す可能性があります。本稿では、この判例が示唆するデータガバナンスの重要性と、日本企業が講じるべき実務的な対策について解説します。
AIは「弁護士」でも「代理人」でもない
米国で注目すべき司法判断が下されました。ある連邦地方裁判所の判事が、捜査対象者が生成AI(チャットボット)に入力したプロンプトや、それによって生成された文書について、「弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege)」の保護対象にはならないと判断したのです。
秘匿特権とは、弁護士と依頼者の間の秘密のコミュニケーションを、裁判などの場での証拠開示から守る法的な権利です。しかし、今回の判断の根底にあるのは、「AIチャットボットとの対話は、弁護士との対話ではない」という極めてシンプルな事実です。たとえその後に弁護士へ送るためのドラフトを作成する目的であっても、AIプラットフォームに入力した時点で、それは第三者(AIベンダー)への情報開示とみなされ、秘匿性が失われる可能性があるという論理です。
日本企業が直面する「ディスカバリー」と「シャドーAI」のリスク
「米国の話であり、日本国内の法的手続きには直結しない」と考えるのは早計です。グローバルに展開する日本企業にとって、米国での訴訟リスクは常に存在し、そこでは「ディスカバリー(証拠開示手続き)」が適用されます。もし、日本本社の法務部やエンジニアが、係争に関連する契約書のドラフト作成や特許文書の翻訳にコンシューマー向けの生成AIを使用していた場合、そのログは証拠として提出を求められる可能性があります。
特に日本では、DeepLやChatGPTなどのツールを、従業員が会社の正式な許可やセキュリティ設定なしに業務利用する「シャドーAI」が常態化しているケースが散見されます。「翻訳するだけ」「要約するだけ」という軽い気持ちで機密情報を入力してしまうことが、法的な防衛ラインを崩す「蟻の一穴」になりかねないのです。
技術的観点からのリスク管理:入力データはどこへ行くのか
この問題の本質は、AIモデルへの入力データがどのように扱われるかという技術的な仕様への理解不足にあります。多くの生成AIサービスの無料版やコンシューマー版では、入力データがモデルの再学習(トレーニング)に利用されたり、サーバーログとして一定期間保持されたりする規約になっています。
企業が導入すべきは、以下の2点を明確に区別した運用です。
- パブリック環境:学習データとして利用される可能性がある。機密情報、個人情報、法的権利に関わる情報の入力は厳禁。
- エンタープライズ環境(API利用含む):「ゼロデータリテンション(データ保持なし)」または学習への利用除外(オプトアウト)が契約で保証されている環境。
しかし、たとえエンタープライズ環境であっても、今回の判例に照らせば「AIに入力した事実」自体は残るため、極めてセンシティブな法的文書の作成プロセスにおいては、AIの介在自体がリスクになる可能性も考慮する必要があります。
日本企業のAI活用への示唆
今回の米国の判断を踏まえ、日本企業の意思決定者や実務担当者は以下の点を見直すべきです。
1. 「AIは第三者」という認識の徹底
AIは社内のツールではなく、外部ベンダーが提供するサービスです。法務相談や内部告発、特許申請前の発明内容など、高度な秘匿性が求められる情報を安易に入力しないよう、社内ガイドラインを更新する必要があります。
2. 契約および設定の再確認
現在利用しているAIツールが、入力データを学習に利用するか否か(オプトアウト設定)を技術的に再確認してください。特に法務・知財部門には、ログが残らない、あるいは高度なセキュリティが担保された専用環境を提供することが推奨されます。
3. リスクベースのアプローチ
すべてのAI利用を禁止するのは現実的ではありません。一般的なマーケティングコピーの作成や公開情報の要約にはAIを積極的に活用しつつ、訴訟リスクや知的財産に関わる業務においては「あえてAIを使わない」、あるいは「ローカル環境(オンプレミスや自社VPC内)で動作するLLMを使用する」といった使い分けが、今後のAIガバナンスの要となります。