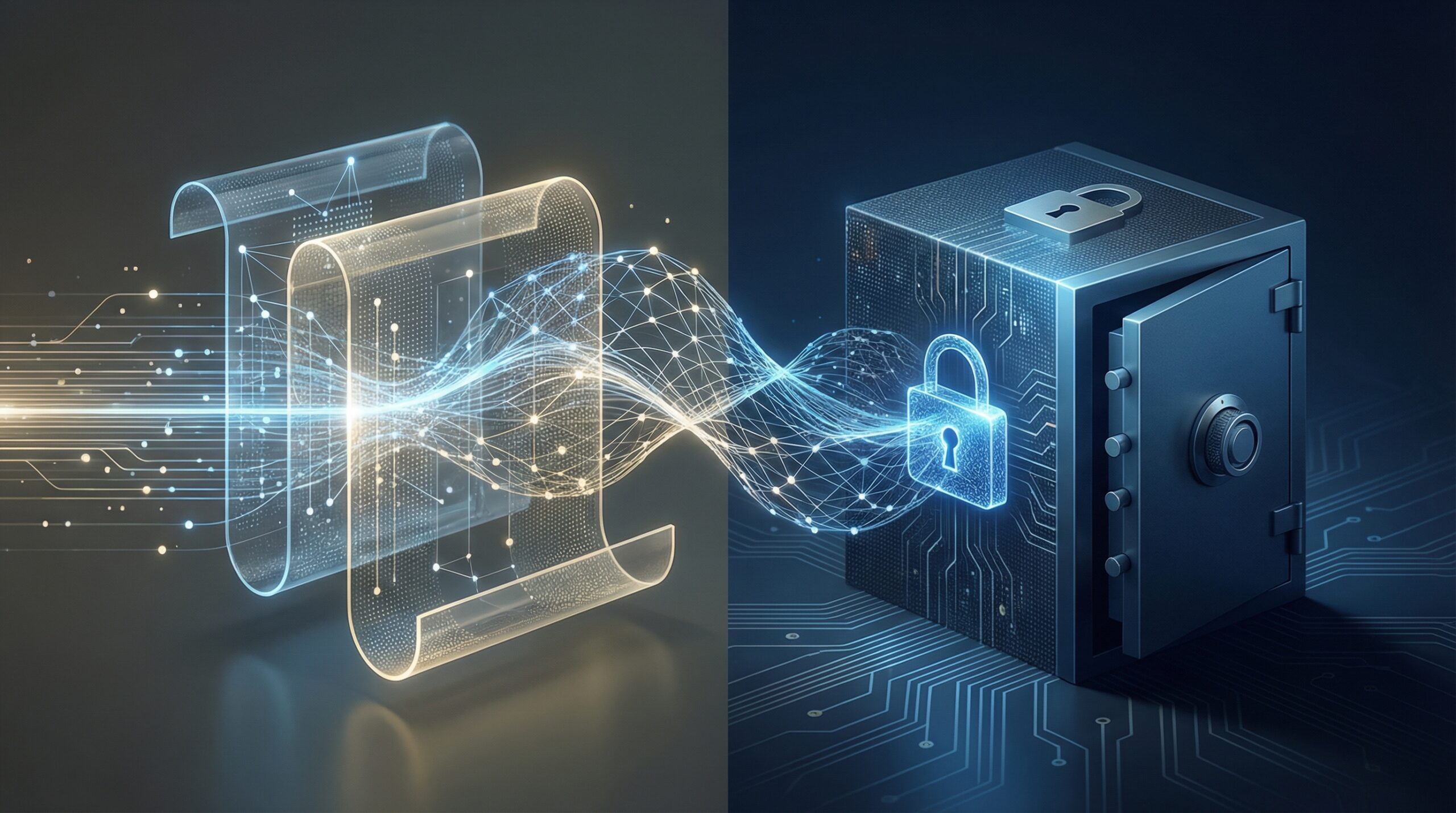米著名投資家マーク・キューバン氏が「AIは企業の特許出願を終わらせるかもしれない」と発言し、波紋を呼んでいます。特許として公開された技術情報が瞬時に大規模言語モデル(LLM)に学習され、回避策(ワークアラウンド)を容易に生成されてしまうリスクがあるからです。本稿では、この発言を端緒に、日本企業が直面する「知財公開のリスク」と「営業秘密(トレードシークレット)の重要性」について解説します。
特許制度の「公開代償」と生成AIの脅威
特許制度は本来、技術を世の中に「公開」する代償として、一定期間の「独占権」を付与する仕組みです。しかし、生成AIの登場により、この前提が揺らぎ始めています。マーク・キューバン氏の懸念は、特許公報として詳細な技術仕様を公開した瞬間、それが世界中のLLMの学習データとなり、競合他社がAIを使って「特許に抵触しない代替案」を瞬時に生成できてしまうという点にあります。
従来、特許の回避設計には高度な専門知識と膨大な時間が必要でした。しかし、最新のLLMは特許請求の範囲(クレーム)を論理的に分析し、その構成要件の一部を置換したり、異なるアプローチで同様の効果を得るコードや設計図を提案したりする能力を飛躍的に高めています。つまり、苦労して取得した特許が、かえって「競合への技術移転」と「回避の手引き」になってしまうパラドックスが生じているのです。
「ブラックボックス化」への回帰と営業秘密管理
この状況下では、独自のアルゴリズムやデータ処理のノウハウをあえて特許出願せず、社外秘の「営業秘密(トレードシークレット)」としてブラックボックス化する戦略が現実味を帯びてきます。AIモデルの学習データセットや、パラメータの調整ノウハウ、プロンプトエンジニアリングの勘所などは、特許よりも秘匿によって競争優位を保ちやすい領域です。
日本には「不正競争防止法」があり、有用な技術上・営業上の情報が「秘密として管理」されていれば、法的な保護を受けられます。しかし、ここで課題となるのが日本企業の組織文化とセキュリティ体制です。単に「出願しない」だけでは法的保護の対象にはなりません。アクセス権限の厳格な管理や、情報の持ち出し防止措置など、客観的に「秘密管理性」が認められる状態を維持する必要があります。
開発スピードこそが最大の防御壁
AI・ソフトウェア領域においては、技術の陳腐化スピードが極めて速いため、特許出願から登録までのタイムラグ(早期審査を使っても数ヶ月〜年単位)の間に、技術トレンドが変わってしまうことも珍しくありません。特許による法的な防御壁を構築している間に、競合はAIを活用して次のイノベーションを起こしてしまいます。
これからの時代、最強の「特許」は法的な権利書ではなく、「他社が追いつけない速度で改善を続けるプロセスそのもの」になる可能性があります。IP(知的財産)部門は、すべての成果を発明として届け出る従来の方針を改め、エンジニア部門と連携して「何を公開(権利化)し、何を秘匿するか」の選別基準を再定義する必要があります。
日本企業のAI活用への示唆
以上の議論を踏まえ、日本の経営層および実務担当者は以下の点に留意してAI時代の知財戦略を構築すべきです。
- 知財ポートフォリオの再評価:「特許出願数」をKPIとする古い慣習を見直す必要があります。AIによる回避が容易なロジック系の技術については、出願せずに営業秘密として管理する「秘匿化戦略」への切り替えを検討してください。
- 厳格なデータガバナンスの構築:特許を出さない場合、社内での情報漏洩対策が生命線となります。特に、従業員が社内情報をパブリックな生成AIに入力してしまい、意図せず「公知の事実」となってしまうリスク(Shadow AI利用)への対策は急務です。
- 「防御」から「スピード」への意識変革:法的な権利保護に過度に依存せず、AIを活用して自社の開発サイクル自体を高速化し、競合が模倣する頃には次のバージョンへ移行しているような「逃げ切り型」の競争力を磨くことが、結果として最強の防衛策となります。