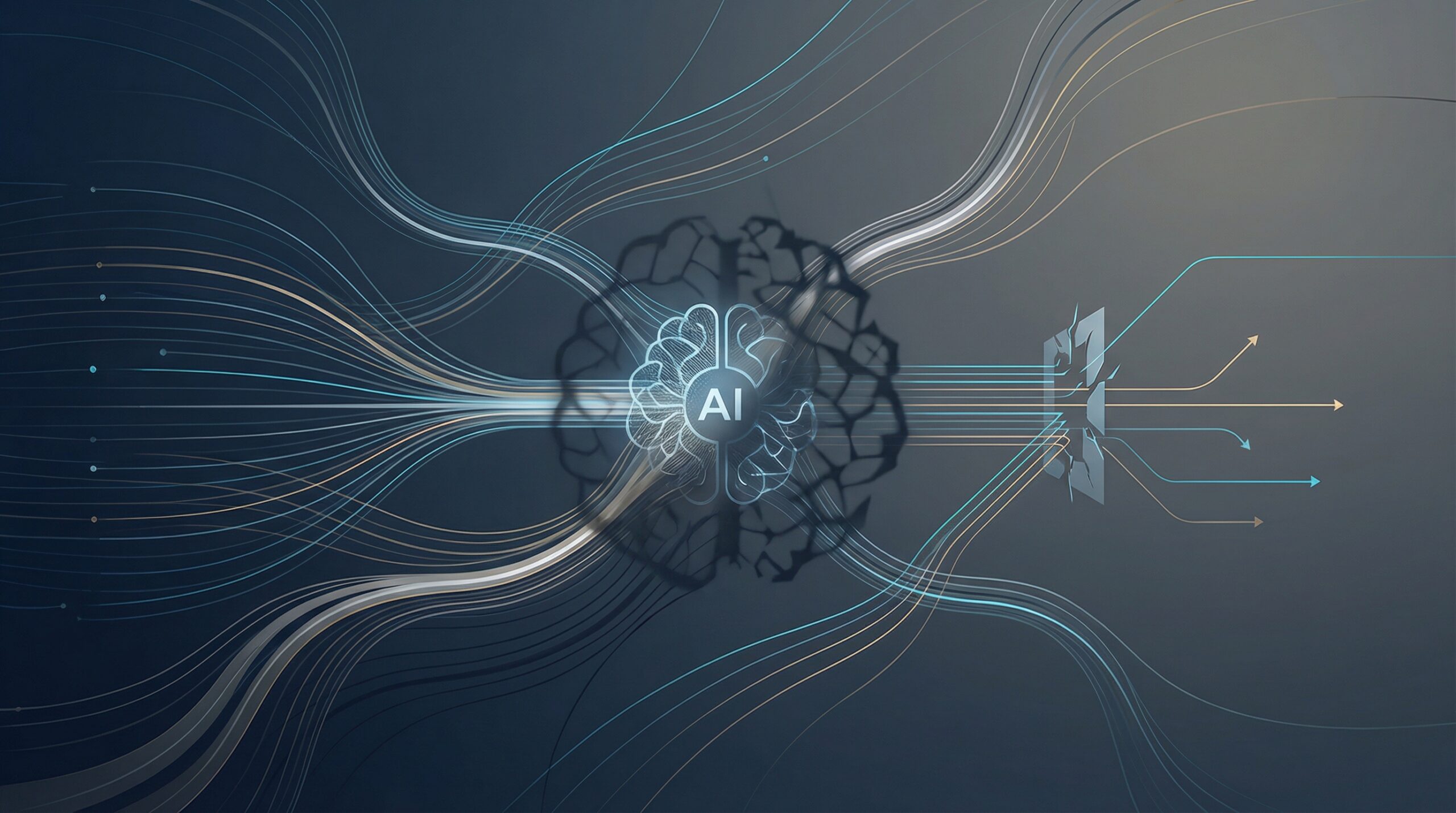生成AIの業務利用が進む中、企業のLLM環境そのものが攻撃者の標的となり始めています。最新の脅威インテリジェンスによると、企業のプロキシ設定の不備を突き、商用LLMのAPIアクセス権を不正に取得する動きが観測されています。本記事では、この新たなリスクのメカニズムと、日本企業が講じるべき具体的な防衛策を解説します。
「学習データ漏洩」だけではない、新たなセキュリティリスク
これまで日本企業が生成AI、特にChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を導入する際、最大の懸念事項は「入力データが学習に利用され、機密情報が漏洩すること」でした。多くの企業がオプトアウト設定や、Azure OpenAI Serviceのようなプライベート環境の構築に注力してきたのはそのためです。
しかし、セキュリティ脅威のトレンドは変化しています。脅威インテリジェンス企業の報告によると、攻撃者は現在、LLMそのものではなく、企業がLLMを利用するために構築した「インフラ」に照準を合わせています。具体的には、商用LLM(OpenAIやAnthropicなど)のAPIにアクセスするためのプロキシサーバーやゲートウェイの設定ミスを探索(Reconnaissance)し、攻撃の糸口を探しているのです。
プロキシとAPIゲートウェイの「設定不備」が狙われている
企業が従業員向けに独自のチャットインターフェースや、社内データを検索するRAG(検索拡張生成)システムを構築する場合、APIキーを一元管理するために中継サーバー(プロキシ)を設置するのが一般的です。
報告されている攻撃手法は、このプロキシ設定の不備(Misconfigurations)を突くものです。ファイアウォール設定のミスや認証の欠如により、外部からアクセス可能な状態になっているプロキシが見つかれば、攻撃者は企業のAPIキーを利用してLLMを無制限に利用できるようになります。
これは、いわゆる「LLMjacking(LLMジャッキング)」と呼ばれるリスクにつながります。攻撃者は、企業のクレジットカードに紐付いたAPI割り当てを勝手に使用し、自身のマルウェア作成やスパム生成、あるいは他者へのサービス再販などに悪用します。結果として、企業は莫大なクラウド利用料を請求されるだけでなく、不正利用の踏み台として加担してしまうリスクがあります。
「とりあえず内製」が生む脆弱性の温床
日本企業、特にDX推進部門やR&D部門では、スピード感を重視してStreamlitやGradioなどのライブラリを使い、簡易的な社内用AIアプリを立ち上げることがよくあります。これ自体はイノベーションのために推奨されるべきことですが、PoC(概念実証)環境がそのままセキュリティ監査を経ずに運用され続けているケースが散見されます。
「社内ネットワーク内だから安全」「URLを知っている人しかアクセスしない」という性善説に基づいた運用は、高度化する攻撃者のスキャンツールに対して無防備です。特にクラウド上にデプロイされたプロキシサーバーにおいて、環境変数の露出や認証不備が放置されていると、格好の標的となります。
日本企業のAI活用への示唆
AIの利活用を進める上で、過度な萎縮は避けるべきですが、足元のガードを固めることは不可欠です。今回の事例から、日本のAI実務者および意思決定者は以下の点に留意すべきです。
- 「出入り口」の総点検:自社で構築したLLMゲートウェイやプロキシが、意図せずインターネットに公開されていないか、または脆弱な認証設定になっていないか、インフラレベルでの棚卸しを早急に実施してください。
- コスト異常検知の仕組み化:APIの利用料やトークン消費量の急激なスパイク(急増)は、不正利用の初期兆候です。予算管理の観点だけでなく、セキュリティアラートとしてコスト監視を行う仕組み(FinOps的アプローチ)を導入してください。
- PoCから本番への厳格な移行基準:「とりあえず動くもの」を業務利用する際、必ず情報システム部門やセキュリティチームによるレビューを挟むプロセスを徹底してください。特にAPIキーのハードコーディングや、環境変数の不適切な管理は厳禁です。
- 最小権限の原則:APIキーには利用上限(クォータ)を設定し、万が一漏洩した場合でも被害を最小限に抑えられるよう、プロジェクトごとにキーを分割するなどの対策が有効です。