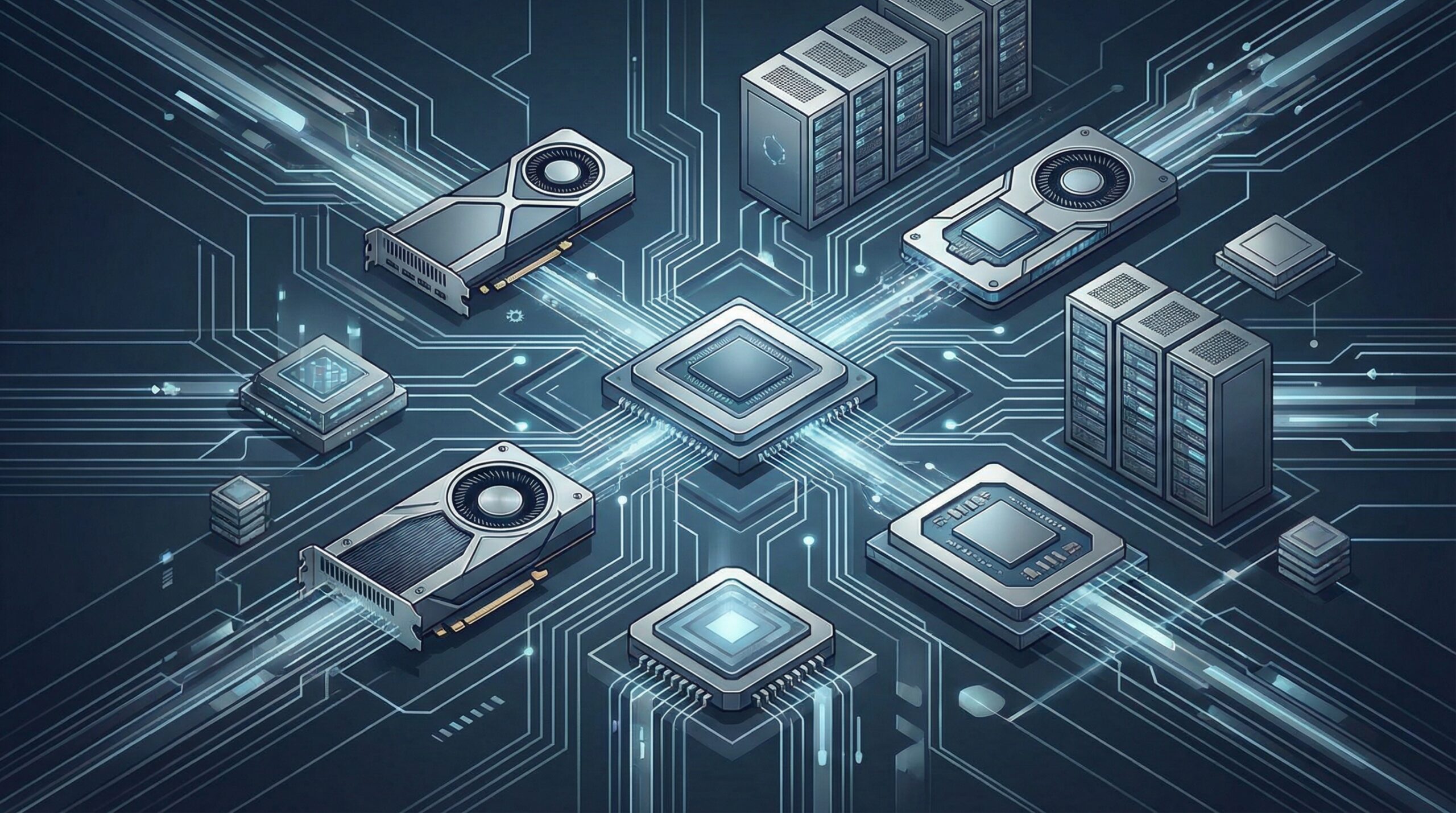生成AIの導入が進む中、多くの企業がGPUなどの計算資源の確保に注力していますが、市場ではそれらを接続する「ネットワーキング技術」への注目が急速に高まっています。海外市場の動向を参考に、日本企業がAI基盤を構築・選定する際に見落としがちなインフラのボトルネックと、実務的な対策について解説します。
GPUだけでは完結しないAIシステムの性能問題
昨今のAIブームにおいて、エヌビディア(NVIDIA)に代表されるGPU(画像処理半導体)の供給不足や価格高騰ばかりが注目を集めてきました。しかし、最新の市場動向を見ると、ブロードコム(Broadcom)やコヒレント(Coherent)といった、いわゆる「非アクセラレータ(non-accelerator)」領域の企業の受注残高が急増していることが分かります。これは、AIシステムのボトルネックが「計算処理」から「データ転送」へと広がりつつあることを示唆しています。
大規模言語モデル(LLM)の学習や推論プロセスでは、複数のGPU間、あるいはサーバー間で膨大なデータのやり取りが発生します。いくら最高性能のGPUを並べても、それらを繋ぐネットワークの帯域幅が狭かったり、遅延(レイテンシ)が大きかったりすれば、データの到着待ちが発生し、高価なGPUがアイドリング状態になってしまいます。つまり、AIインフラの投資対効果(ROI)を最大化するためには、計算資源だけでなく、スイッチや光通信モジュールといった「足回り」の強化が不可欠なのです。
日本企業が直面するインフラ選定の課題
日本国内においても、生成AIを業務フローに組み込む動きが加速していますが、インフラ選定において「GPUのスペック」に偏重する傾向が見受けられます。特に、機密情報の漏洩を防ぐためにパブリッククラウドではなく、オンプレミス環境や専用のプライベートクラウド(ソブリンクラウド)を構築しようとする企業の場合、ネットワーク設計の不備は致命的です。
例えば、社内データを活用したRAG(検索拡張生成)システムを構築する場合、ベクトルデータベースとLLM間の高速なデータ転送が求められます。ここで従来の業務システム用のネットワーク構成を流用すると、レスポンスの遅延を招き、ユーザー体験(UX)を損なう可能性があります。また、データセンターの電力消費量が社会問題化する中、従来の銅線ケーブルよりも電力効率が良い光インターコネクト技術の採用は、企業のESG経営(環境・社会・ガバナンス)の観点からも無視できない要素となりつつあります。
ベンダーロックインのリスクと標準化技術
AIネットワーキングの分野では、特定のベンダーが提供する独自規格(InfiniBandなど)と、より汎用的なイーサネットベースの技術が競合しています。日本企業、特にSIerに依存しがちな組織構造を持つ企業にとって、特定のハードウェアに過度に依存するベンダーロックインは、将来的なコスト増大や拡張性の欠如につながるリスクがあります。
現在、グローバル市場では、AIワークロードに最適化された高速イーサネット技術への投資が進んでおり、よりオープンで調達しやすいエコシステムが形成されつつあります。自社のAIサービスを長期的に運用・拡大していく計画がある場合、目先の性能だけでなく、調達の安定性や技術の標準化動向を見極める視点が、エンジニアやプロダクトマネージャーには求められます。
日本企業のAI活用への示唆
今回の市場トレンドから、日本企業がAI活用を進める上で意識すべき点は以下の通りです。
- インフラ全体を俯瞰した投資計画:GPU単体の性能だけでなく、ストレージやネットワークを含めたシステム全体のバランスを評価すること。特にクラウド選定時は、インスタンス間の通信帯域やレイテンシの仕様を確認する必要があります。
- データ転送コストとセキュリティの精査:ハイブリッドクラウド構成(オンプレミスとクラウドの併用)の場合、外部へのデータ転送コスト(Egress Cost)や通信経路の暗号化強度が課題となります。ネットワーク設計の初期段階でこれらを織り込むことが重要です。
- 「つなぐ技術」への感度を高める:AIの進化は計算速度だけでなく、通信速度の進化とセットで語られるべきです。インフラ担当者だけでなく、意思決定者も「ネットワークがAIの性能を左右する」という認識を持ち、適切なリソース配分を行うことが成功の鍵となります。