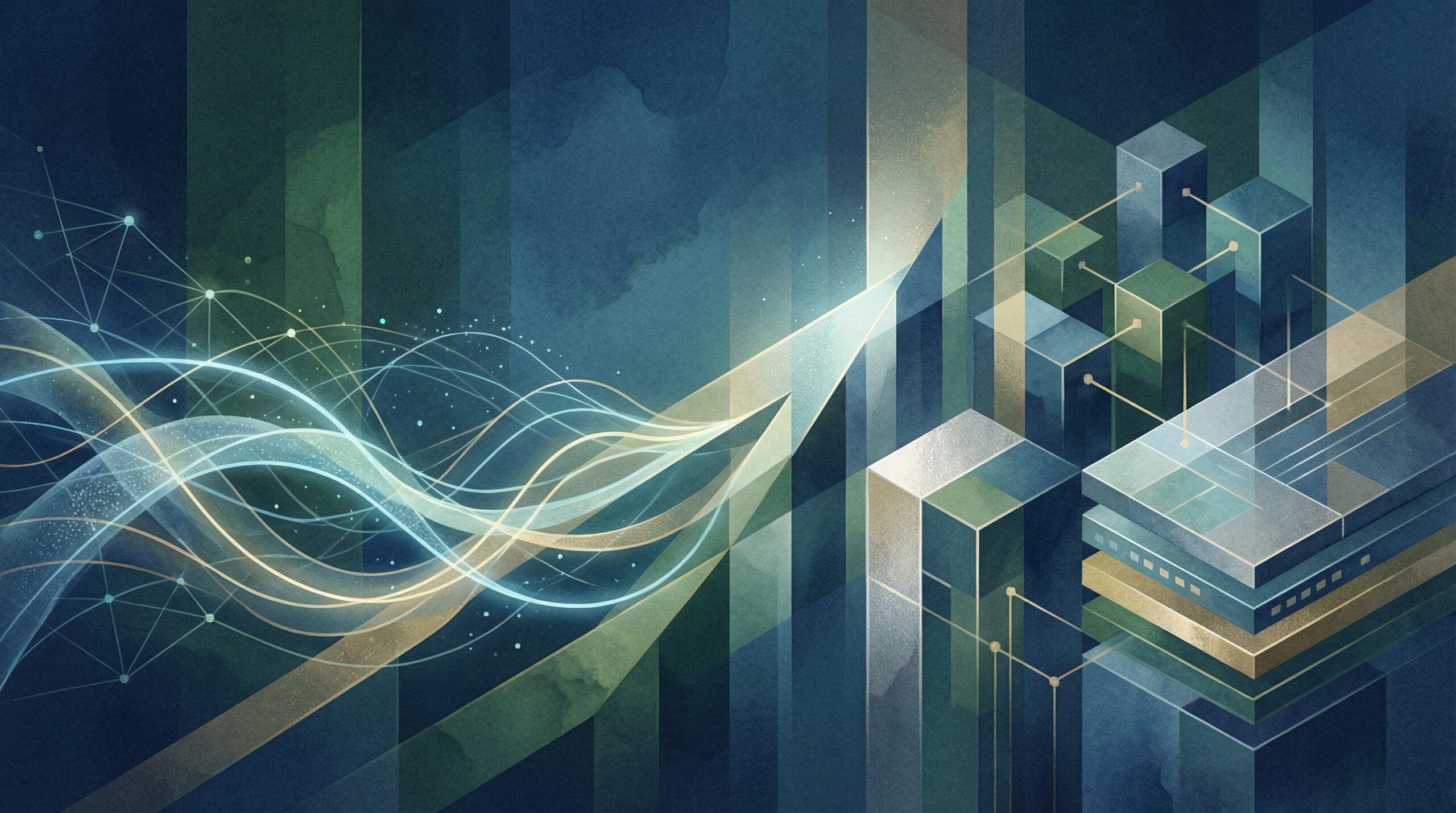生成AIブームが一巡し、市場は過度な期待から実用性(ROI)を重視するフェーズへと移行しつつあります。米国市場におけるSalesforceの「Agentforce」戦略とOracleのインフラ動向は、今後の企業AI活用における重要な二つの潮流――「自律型エージェント」と「堅牢なデータ基盤」――を象徴しています。本稿では、これらの動きを参考に、日本企業がとるべき現実的なAI戦略について解説します。
「Copilot」から「Agent」へ:Salesforceが描く業務自動化の次の一手
米国市場においてSalesforceの株価収益率(PER)が20倍前後で推移しているという事実は、投資家がAIに対して冷静な実益を求め始めていることを示唆しています。ここで注目すべきは、同社が強力に推進している「Agentforce」です。
これまでの生成AI活用は、人が指示を出しAIが支援する「Copilot(副操縦士)」型が主流でした。しかし、Agentforceが目指すのは、AIが自律的にタスクを計画・実行する「Agent(エージェント)」型へのシフトです。例えば、顧客からの問い合わせに対し、AIが回答を作成するだけでなく、CRM(顧客関係管理)システム内のデータを参照し、必要に応じて返品処理や配送手配までを完結させるような動きです。
日本のビジネス現場、特に深刻な人手不足に悩むカスタマーサポートや営業事務において、この「自律的に動くAI」は大きな省力化の鍵となります。ただし、AIにアクション権限を持たせることは、誤動作(ハルシネーション)によるリスクも増大させます。日本企業がこれを導入する場合、どの権限までをAIに委譲し、どこで人間が承認(Human-in-the-loop)を行うかという、細やかな業務設計が求められます。
Oracleの動向に見る「レガシーデータ」とAIの融合
一方、Oracleの株価変動や市場評価は、エンタープライズITにおける「守り」の重要性を再認識させます。AIモデルそのものの性能競争が注目されがちですが、実務において最も重要なのは「自社の固有データをいかに安全にAIに食わせるか」です。
多くの日本企業において、基幹システムやデータベースはOracle製品を含むレガシーな環境で稼働しています。Oracleが推進するAI戦略は、こうしたミッションクリティカルなデータを、セキュリティを担保したままクラウドやAIサービスと連携させる点に強みがあります。AI活用のためにデータを無理やり新しいプラットフォームに移管するのではなく、既存のデータ資産を生かしたまま、RAG(検索拡張生成)などを通じてAIと接続するアプローチは、リスクを嫌う日本の組織文化とも親和性が高いと言えます。
日本企業のAI活用への示唆
1. 「対話」から「代行」へのロードマップ策定
チャットボット導入で満足するのではなく、定型業務を自律的に遂行させる「エージェント化」を視野に入れるべきです。ただし、いきなり全自動化するのではなく、リスクの低い社内業務から開始し、AIの挙動を監視するガバナンス体制を構築することが先決です。
2. 既存資産(レガシーデータ)のAI対応化
AI活用を急ぐあまり、データ基盤の整備を疎かにしてはいけません。特に金融や製造など高い信頼性が求められる業界では、Oracleのような堅牢なデータベースとAIをどう接続するかというインフラ設計が、長期的には競争力の源泉となります。
3. ベンダーロックインとコスト管理のバランス
SaaSベンダー(Salesforce等)の組み込みAI機能を利用するのは手軽ですが、長期的にはコスト増やベンダーロックインのリスクがあります。自社開発すべき領域と、SaaSの機能をそのまま使うべき領域を明確に区分けし、2026年以降を見据えた持続可能なIT投資計画を立てることが重要です。