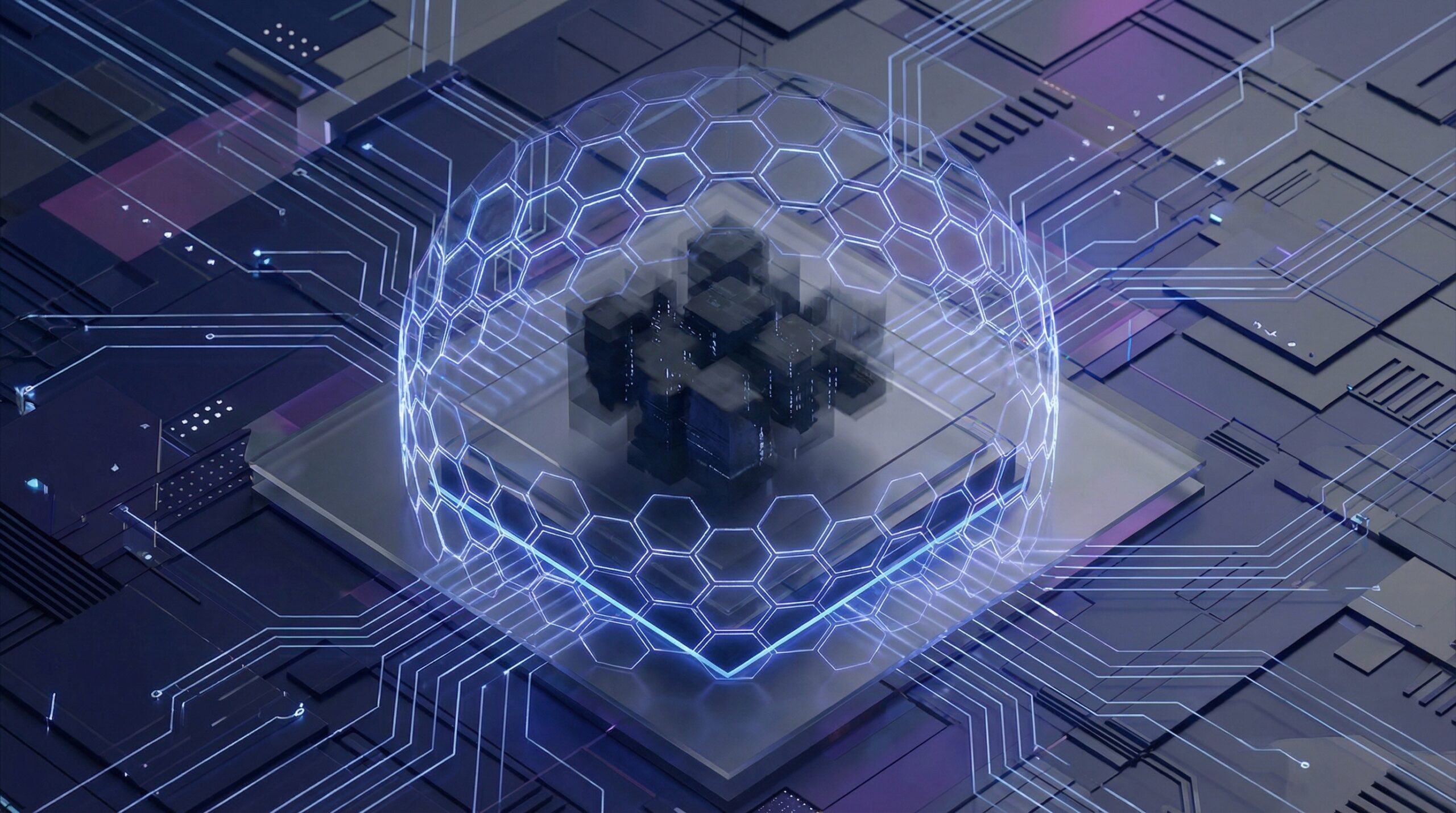生成AIの業務利用が急速に進む中、従業員が許可なくAIツールを利用する「Shadow AI」や、AIシステム自体を狙った新たな脅威が課題となっています。一律の禁止ではなく、イノベーションを阻害せずにリスクを管理するための「可視化」と「AI検知・対応(AIDR)」の重要性について解説します。
「禁止」から「監視」へ:セキュリティパラダイムの転換
生成AI(Generative AI)の登場以降、多くの日本企業が直面している最大のジレンマは、「業務効率化のためにAIを使わせたいが、情報漏洩やコンプライアンス違反が怖い」という点にあります。初期段階では、ChatGPTなどのアクセスを一律に禁止する企業も少なくありませんでした。
しかし、CrowdStrikeなどのセキュリティベンダーが提唱する最新の「AI Detection and Response(AIDR)」という概念は、このアプローチが限界に来ていることを示唆しています。従業員は業務を遂行するために、会社の監視網を抜けて個人用デバイスや未承認のAIツール(Shadow AI)を利用する傾向にあるからです。
これからのセキュリティは、AIの利用を「止める」のではなく、誰が・どのツールを・どのように使っているかを「可視化」し、異常な振る舞いやリスクの高いデータ送信をリアルタイムで検知・対応する方向へシフトする必要があります。
AIエージェントと新たな攻撃対象領域
単なるチャットボットの利用にとどまらず、自律的にタスクをこなす「AIエージェント」や、社内システムに組み込まれたLLM(大規模言語モデル)の普及も進んでいます。これは、攻撃者にとっても新たな攻撃対象(アタックサーフェス)が広がることを意味します。
例えば、AIモデルに対する「プロンプトインジェクション(AIに特殊な命令を与えて本来の制限を回避させる攻撃)」や、学習データの汚染、機密情報の引き出しなどが懸念されます。従来のウイルス対策ソフトやファイアウォールだけでは、こうした「言語ベース」の攻撃や、AIの正常な振る舞いに偽装した不正活動を検知することは困難です。
したがって、AIの挙動そのものを監視し、AIシステムが侵害された際や、AIが悪用された際に即座に対応できる専用のセキュリティレイヤー(AIDR)の整備が、システム開発や導入の要件として求められるようになってきています。
日本企業の組織文化と「Shadow AI」のリスク
日本企業においては、稟議制度や厳格な承認プロセスが存在する一方で、現場レベルでのデジタルツールの導入管理が追いついていないケースが散見されます。特に、「翻訳」や「要約」といったタスクで、従業員が悪意なく無料のAIツールに機密データを入力してしまうリスクは、欧米以上に高い可能性があります。
また、日本独自の商習慣として、取引先との契約書や仕様書の取り扱いが非常にセンシティブであることが挙げられます。もし、従業員が契約書の内容を学習データとして利用される設定のままパブリックなAIに入力してしまえば、深刻な信頼毀損につながります。
「見えないもの」は管理できません。まずは自社内でどのようなAIツールが実際に使われているのかを、ネットワークログやエンドポイントセキュリティ(EDR)の仕組みを活用して洗い出すことが、ガバナンスの第一歩となります。
日本企業のAI活用への示唆
グローバルのセキュリティ動向と日本の実情を踏まえ、以下の3点を実務上の指針として提案します。
1. 「全面禁止」から「ガードレール付きの許可」への移行
AI利用を全面的に禁止すると、Shadow AI(隠れた利用)を助長し、かえってリスクを高めます。認可された安全なAI環境を整備し、そこでの利用ログを監視する体制を作る方が、結果としてセキュリティレベルは向上します。
2. セキュリティツールの「AI対応」を確認する
現在導入しているEDRやセキュリティ監視ツールが、AIツールの利用状況を可視化できるか、あるいはAI特有の脅威(プロンプトインジェクション等)に対応するロードマップを持っているか、ベンダーに確認すべきです。CrowdStrikeのような主要ベンダーは既にAIDR機能の強化に動いています。
3. AIガバナンスと従業員教育のセット運用
技術的な監視だけでなく、「何がリスクなのか」を従業員に教育することが不可欠です。特に日本では「知らなかった」によるインシデントが多いため、具体的なNG事例(個人情報、顧客データの入力禁止など)を明示したガイドラインを策定し、定期的に周知する必要があります。